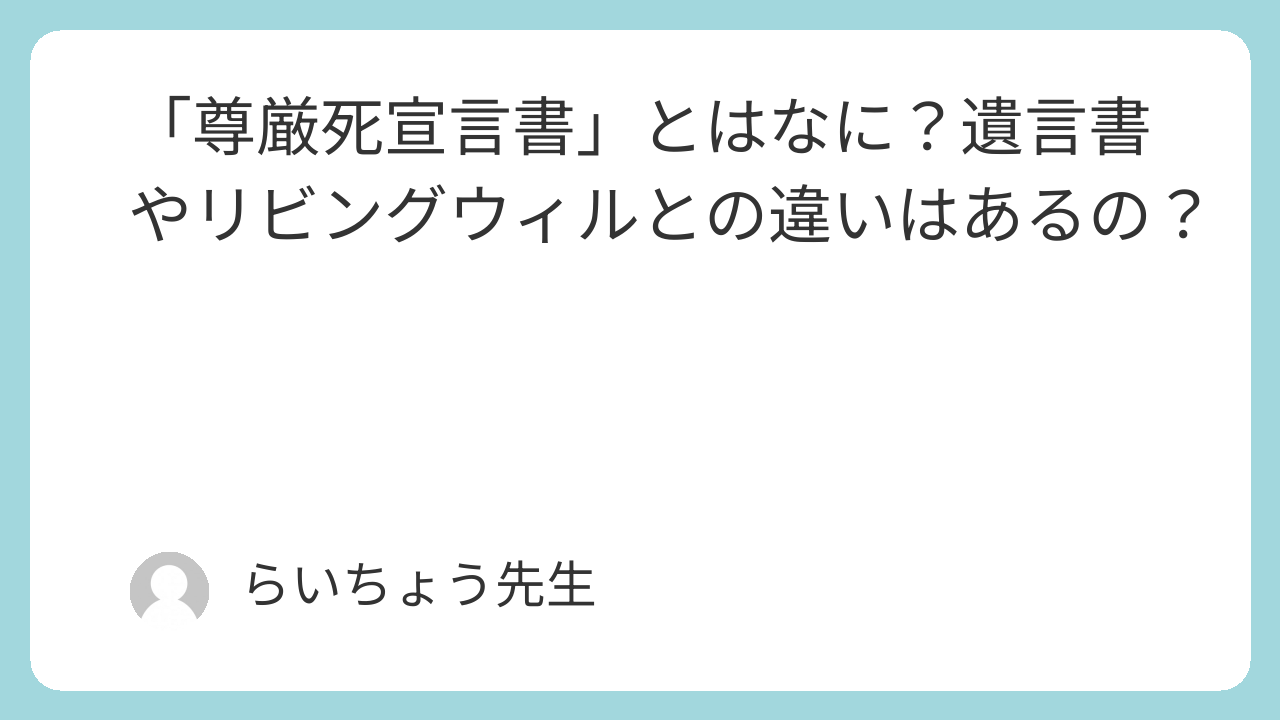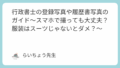看護師・社会福祉士・精神保健福祉士として20年近く医療福祉の現場にいた経験をもとに、
今は行政書士として終活のサポートしています。
実は稀少なエキスパートです🌿
今日のテーマは「尊厳死宣言書(リビングウィル)」について。
「そもそも尊厳死宣言書ってなに?」
「リビングウィルと尊厳死宣言書の違いは?」
などの疑問を明らかにしていきます!
■ 尊厳死宣言書とは何?
「尊厳死宣言書」とは、
回復の見込みがない状態になったときに、自分の望む医療やケアの方針を伝えるための文書です。
もっとわかりやすく言うと、元気なときに
「もしも意識がなくなって、自分で話せなくなったら──
私は延命治療は希望しません。
穏やかに、自然に看取られたいです。」
こういう思いを、元気なうちに書き残しておくものです。
医療の現場では「リビングウィル(Living Will)」という名前で呼ばれることもあります。
公正証書という信頼性の高い作り方でつくるリビングウィルだと思ってください。
■ リビングウィルと尊厳死宣言書は同じなの?
はい、基本的には同じものと考えて大丈夫です。
「尊厳死宣言書」は日本での呼び方、
「リビングウィル」は欧米由来の名称で、
いずれも延命治療に関する意思表示を記録する文書です。
ただ、医療や介護の現場では「リビングウィル」の方がよく使われていて、
「尊厳死=安楽死」と誤解されるのを避けるために、あえてそう呼ぶ施設も多いです。
違いは、どのくらい効果が発揮できるかという部分です。
尊厳死宣言書は公正証書で作成するため、医療現場で受け止められる意思の重さが
自由に個人が書き残しているようなリビングウィルとは比較にならないほど重要視されます。
しっかりとした効力を求めるなら市販のエンディングノートの中の1ページにあるようなリビングウィルではなく、公正証書尊厳死宣言書なのです。
内容についても違いはありませんが、「延命治療をしない」内容に対して
「フルセットで救命も延命治療もして欲しい」という内容で作成することも出来ます。
尊厳死宣言書と言う名前だと、延命治療を避けたい人が書くイメージになってしまうのはちょっと問題点ですね。
■ 尊厳死宣言書と遺言書の違いは何?
ここ、ちょっとややこしいですが大事なポイント!
全然違うんですよ!
尊厳死宣言書(リビングウィル)
内容→医療・ケアに関する希望
効力がある時 →生きている間(終末期など)
主な目的 →延命治療の希望を伝える
自分自身の為に書く意味合いが強い。
作成の方法→色々(公正証書がオススメだが自分でも書ける)
遺言書
内容→財産・相続・死後の手続き
効力があるとき→死後
主な目的→財産の配分や遺族への想いを伝える
作成方法→色々(公正証書、自筆、エンディングノートなど)
「遺言書は死後のため」
「尊厳死宣言書は生きているうちの“最期”のため」ということなんです。
無理な延命治療をして苦しい最期になりたくない!
自然な寿命を迎えたい!
という希望があるならば尊厳死宣言書を自分の為にも作っておくという事ですね。
遺言書とセットで作ることは出来ますが、遺言書の中に尊厳死宣言を盛り込むことは出来ません(;゚ロ゚)
■ 尊厳死宣言書は、いつ必要なの?
たとえば──
• 意識が戻らない状態で本人が人工呼吸器をつけるか判断ができない
• 認知症が進んで、意思表示が難しくなった
• 余命が限られていて、治療方針を自分で選びたい
こんなとき、医療者や家族は「本人はどうしたいんだろう?」と迷います。
そんなときに、事前に残しておいた尊厳死宣言書が判断の助けになります。
高齢になってきて、嚥下能力が落ちてきて自分の口から食べられなくなってきたとき
誤嚥性肺炎になった時も鼻からの栄養や胃瘻など、望まない延命処置を避けることが出来ます。
20年以上臨床の現場にいると、実は一番出番があるのが高齢者の入院時だと思います。
誰にでも訪れます。
80歳を過ぎると、自由に字が書けなくなったり、年齢相応の物忘れが出てきたりします。
足腰も弱くなってくるので病院には子供などに付き添ってもらいます。
そうすると、このご時世、いろんな書類がいっぱい出てきてその中に「治療方針に関する意思確認」なんていう書類がしれっと入っています。
要は、何かあったときにどうしますか?
フルセットで救命しますか?ANR
それとも、しませんかDNR
というような書類です。
なにも知らない家族が、フルセットで救命ANRに○をつけてしまうと、そのような対応になりますね。
勿論、望まない延命処置、苦しい積極的治療も行われます。
あれれ、自分の意思は?
建前では患者の意思を優先しますが、このご時世、家族の意思は無視できないのが現実です。
ましてや、認知症になった場合の治療決定は家族の意向がほぼ優先されていますね、残念ですが。
元気なときに未来の自分を守る意思表示を 尊厳死宣言書 で残していきましょう!
■ 誰が見ても「意思がわかりやすい」ようにするには?
尊厳死宣言書は、ただ自分でメモに書くだけではなく
公正証書で正式に作ることで信頼性がグッと高まります。
メモが悪いわけではないのですが、医療福祉現場では、常に責任という重圧がのしかかります。
その意思表示がどの程度本気なのかという点は非常に重要なのです。
誰が見ても、自分の意思がわかりやすい=意思を実現してもらいやすい
すでに重要性に気づいた人たちが尊厳死宣言書を作り始めています。
医療福祉現場で働いている人からの依頼が多いことが、いかにこの書類に力があるかを証明しています。
その作り方や費用、必要書類などについては、次回のブログで詳しくお話ししますね😊
✍️ まとめ
• 尊厳死宣言書は、「自分らしい最期」を準備するための文書
• 医療や延命についての意思を、元気なうちに記しておくもの
• 遺言書とはちがい、生きているうちに使われる“命の意思表示”
• 医療福祉の現場では「リビングウィル」として理解されている事が多い
(作成方法によって効力の程度に差はある)
次回は
「尊厳死宣言書を公正証書で作る理由と費用」について書いていきます。
シリーズで書いているのでトップページ右の検索窓に尊厳死宣言書と入れてみてください。
わかりやすく、簡単にをモットーに
みなさんの“もしも”にそなえるお手伝いをしていきます🌿