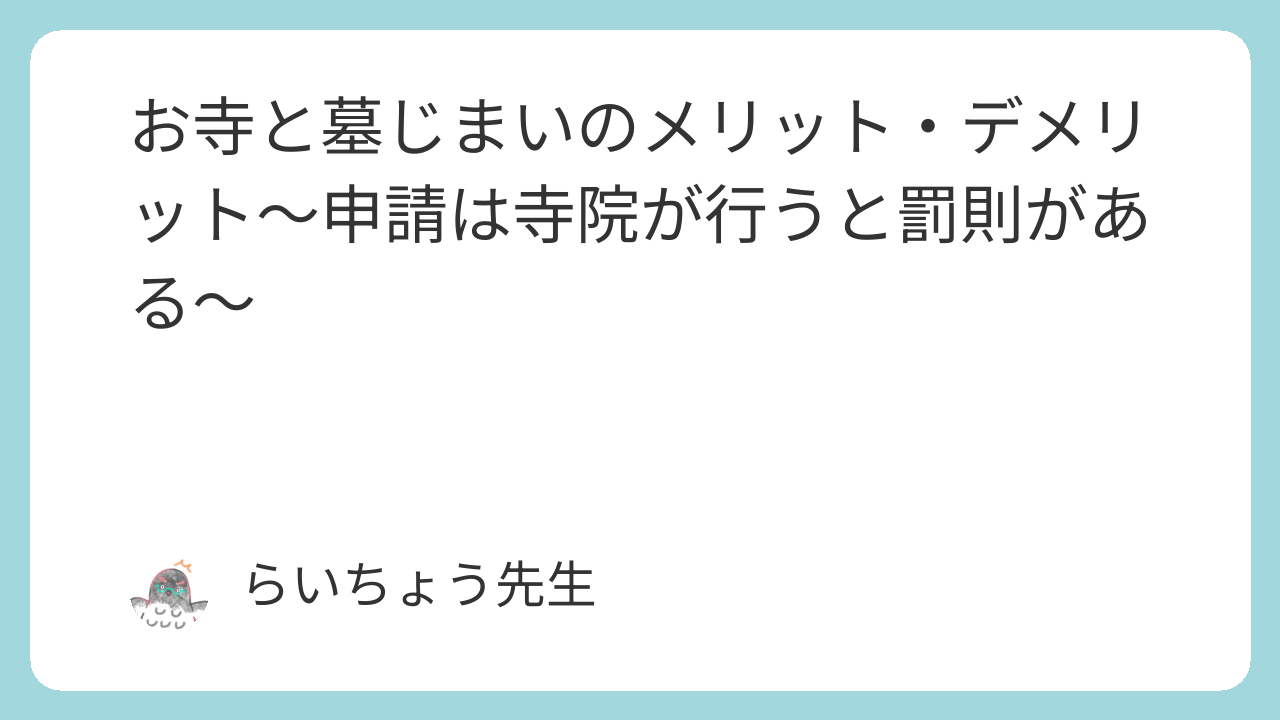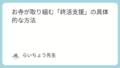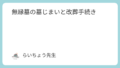墓じまいは檀家にとって大きな決断であり、お寺にとっても一大事。
本記事では住職から見た墓じまいのメリット・デメリットに加え、墓地埋葬法に基づく改葬手続きや必要書類、行政書士が関わる意義を解説します。
2026年の行政書士法改正で官公庁に提出する書類は行政書士以外の者が有償で作成・申請できなくなります。
厳しい罰則があるため要注意です。
1. 住職から見た墓じまいのメリット
- 無縁墓の減少:承継者不在の問題を未然に防ぎ、将来の管理負担を軽減。
見た目に荒れている墓は檀家を不安にさせます。 - 永代供養への移行:納骨堂や永代供養墓への移行により、新しい供養の形を提示できる。
新たな収入源。受け入れ条件にもよるが檀家は増加する可能性がある。 - 境内整備の機会:墓石撤去を契機に、境内環境を整備しやすくなる。
2. 住職から見た墓じまいのデメリット
- 檀家数の減少:墓じまいが進めば、法要や布施収入の減少につながる。
- 関係性の希薄化:「お墓がなくなる=お寺とのつながりが薄れる」という心理的影響。
- 文化継承の問題:代々の墓を整理することによる文化的・感情的な喪失感。
- 散骨など教義上相容れないお骨の行き先: 先祖とのつながりを重視する教義のなかで、お骨がなくなってしまう散骨に抵抗感がある。
3. 墓じまいに必要な届出(改葬手続き)
墓じまいを行う際には墓地埋葬法第5条に基づき、市町村長の許可を受ける必要があります。
これは「改葬」と呼ばれ、一度埋葬された遺骨を別の墓地・納骨堂・永代供養墓へ移す手続きを意味します。お墓のお引っ越しですね。
ですので、散骨や再火葬の場合は一部取り扱いが異なります。
主な必要書類
- ① 改葬許可申請書:
現在の墓地がある市町村役場へ提出する。申請人は原則として祭祀承継者。 - ② 改葬受け入れ証明書(受け入れ承諾書):
改葬先の墓地・納骨堂の管理者が発行する「受け入れ承諾」の証明。 - ③ 納骨証明書(埋葬・収蔵証明書):
現在の墓地・納骨堂の管理者(寺院や霊園)が発行し、「遺骨が確かに収蔵されている」ことを証明する書類。
これらの書類が揃って初めて、市町村から改葬許可証が交付され、遺骨を移動できます。
4. 行政書士法と手続き代行の制限
行政書士法により、他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士のみと定められています。
したがって、石材店や寺院が有償で改葬許可申請を代行することは法律上できません。
無償でのサポートは可能ですが改正行政書士法では「いかなる名目でも報酬を得て行うことができない」と変更されます。これは、たとえば、コンサルティング料、サービス料など他の名目でも対価として報酬を得ての申請代行はできないという事です。
本人申請と言う形で、記載の手伝いをすることもNGです。
違反した場合は100万円以下の罰金のほか、拘禁1年以下という厳しい刑罰が科されます。
今まで通りという感覚は通用しない時代になりました。
高齢の檀家さんや遠方の檀家さんとの関係を鑑みると、専門家を入れて適正価格でのワンストップサービスをすぐに提供出来るというのがお寺にとっては一番メリットがあると思います。
5. 離檀料の考え方
墓じまいの費用は大きく以下に分かれます。
- 改葬許可申請の費用:行政書士への依頼報酬。
- 墓石撤去・整地費用:石材店に依頼する工事費用。
- 新しい納骨先の費用:納骨堂・永代供養墓・散骨などの費用。
- 離檀料:お寺とのこれまでの関わりに感謝する意味でお渡しするお布施的性質のもの。金額は数万円~数十万円と幅広いが、檀家とお寺の信頼関係を保つことが最も大切。
墓じまいで一番多いのが離檀料トラブル。法的には支払を強制できる性質のものではありません。
今はSNSなど情報の拡散が素早く適正価格で折り合いをつけることがよろしいかと思います。
交渉や訴訟は弁護士しか許されていない為、行政書士では対応出来ません。
相手が弁護士を立ててきた場合対応費用はそれなりに高額になります。
もめない程度、一般的に法事2~3回程度が相場です。
お寺としては閉眼供養、もし自身の宗教法人内での改葬の場合は開眼供養、その他法事などのつながりは残り収入機会は保たれています。
この記事をお読みのご住職には、無用の心配ですが、墓に張り紙を貼ったりするとすぐに口コミや写真、動画で拡散されます。
離断料は感謝として支払いたいという檀家さんも多いので提案方法が重要になるかと思います。
6. 行政書士が関わるメリット
- 法的に安心:行政書士が関与することで、改葬手続きが適法に進められる。
- お寺や石材店の負担軽減:本来できない手続き業務を背負うリスクを回避できる。
- 終活全般への広がり:相続・遺言・死後事務など終活に関連する課題にもワンストップで対応可能。
- 高齢・遠方の檀家さんでもスムーズに進められる:手間がかかると人間はイライラするので間接的なトラブル予防です。
まとめ
墓じまいは、お寺にとって檀家数や文化継承への影響を伴う一方で、無縁墓の減少や永代供養への移行といったメリットもあります。
また、改葬は墓地埋葬法に基づく正式な手続きであり、改葬許可申請・受け入れ承諾書・納骨証明書などの書類が必要です。
行政書士法により、これらを有償で代行できるのは行政書士だけです。
寺院が檀家から墓じまいの相談を受けた際は、行政書士と連携することで法的にも安心し、檀家との信頼関係を損なうことなく円滑に進められます。
富山県内で墓じまいを検討されている寺院・檀家様は、どうぞお気軽にご相談ください。
【対応エリア】
富山県全域(富山市・高岡市・射水市・魚津市・黒部市・滑川市・砺波市・南砺市・氷見市・小矢部市・ 上市町・立山町・入善町・朝日町)に対応しております。
上記以外の地域の方も、まずはお気軽にご相談ください。