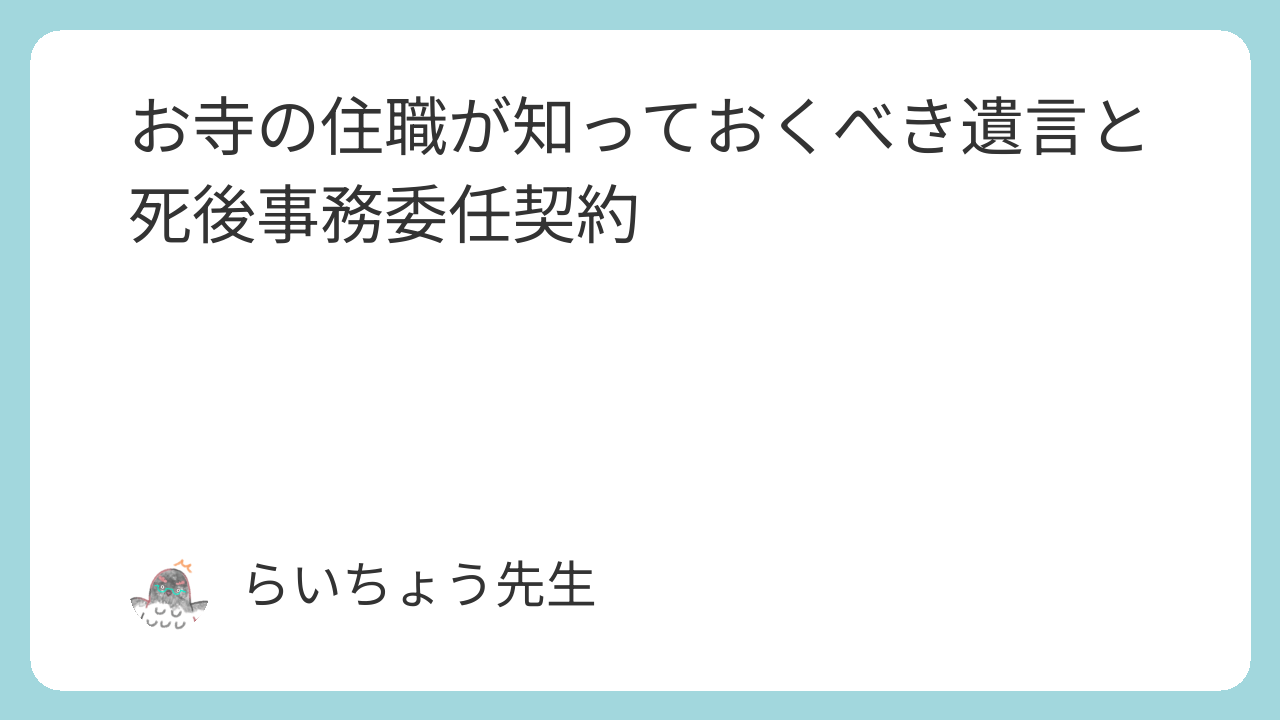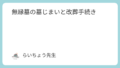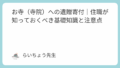「死んだらお寺さんに寄付したい」「死んだら住職に葬儀をお願いしたい」——檀家からよく耳にする言葉ですが、どう対応していますか?法的に実現するには手続きが必要です。
高齢になると宗教はその存在価値を増し、心の寄る辺となる傾向があります。
またおひとり様など、相続人不存在のケースもあり今後宗教法人が遺贈の受け入れを行う事も増えてくるのではないでしょうか。
1. 遺言とは
遺言は、本人が亡くなった後に法的効力をもって実現できる事項を記す唯一の方法です。
民法により、遺言で定められる内容は決まっています(「法定遺言事項」)。代表的なものは以下です。
- 財産の承継先の指定(相続分の指定、遺贈)
- 遺言執行者の指定
- 認知、相続人の廃除やその取消し
- 祭祀承継者の指定(仏壇・墓などを承継する人)
つまり、「財産の処分」は遺言でしか効力を持たせられません。
「死後に寄付したい」という希望を実現するには、必ず遺言で『遺贈』として明記してもらう必要があります。
一方で、葬儀をあげて欲しいという要望に対しては遺言では無く死後事務委任契約で実現していく事になります。
また、相続人がいないおひとり様の場合、遺言執行者の指定は必須事項です。
行政書士は、檀家さんがお元気なときから介入し、あらかじめ遺言を作成、他契約を整えます。
見守り契約→認知症になれば成年後見人→死亡時の死後事務委任契約、遺言執行という形で最後まで意思を形にする伴走支援者でもあります。
2. 遺言における寺院寄付の注意点
- 遺贈の明記が必須:「死んだらお寺に寄付する」という口約束や遺言以外の書類では効力がなく、遺産は自動的に相続人に承継されます。
- 遺留分への配慮:相続人には法律で保障された「遺留分」があります。
遺留分を侵害する遺贈は争いの原因となるため、相続人の人数や関係を踏まえて内容を調整する必要があります。
たとえ、寺院に全部遺贈するという意思でも法定相続人にの遺留分は勘案しておかないと面倒なことになるため遺言作成者には「実現できる遺言」の作成能力が求められます。 - 遺言執行者の指定:実際に遺贈を実行する人を遺言で指定しておくと手続きがスムーズです。
- 実行力のある遺言:ご自分でも遺言を作れない訳ではありませんが「実行力」のある遺言を一般人が作成することはややハードルが高いと考えます。生前整理のタイミングやアドバイスも含めて行う事ができる専門家を選ぶことが重要です。
また、高齢の専門職の場合依頼者の死亡より先に廃業するリスクもあるため、専門職の年齢も重要な選定ポイントです。
3. 死後事務委任契約とは
遺言でできるのは「財産に関すること」ですが、死後には財産以外の多くの事務が発生します。
これを担保するのが死後事務委任契約です。
- 葬儀・通夜・納骨の実施
- 病院・施設からの退去手続き
- 役所への各種届出
- 永代供養の申込み
- 公共料金や家賃の精算
これらは遺言には記せず、死後事務委任契約によって初めて実現可能です。
住職が契約の存在を理解していれば、檀家の希望(例:「必ず○○寺で葬儀をしてほしい」)を法的に担保できます。但し、相続人がいるケースでは相続人の理解が不可欠です。
一般的にご葬儀は残される人たちのけじめの意味合いも大きく親族が行う事が多いからです。
実行されてしまった場合、やり直しまではできません。
4. ケースで考える
ケース①「死んだらお寺さんに寄付したいの」
この希望を実現するには、遺言に「○○寺に財産の一部を遺贈する」と書いてもらう必要があります。
遺言がなければ寄付は法的に無効となり、相続人が拒否すれば実現できません。
また遺留分に配慮しないと相続人から争いが起こる可能性もあるため、行政書士など専門家の助言が欠かせません。
ケース②「死んだら住職に葬儀を頼むよ」
葬儀の執行権は相続人にあり、本人の希望だけでは効力がありません。
この希望を法的に担保するには、死後事務委任契約で「葬儀・納骨を○○寺住職に依頼する」と定めておく必要があります。
住職がこの制度を知っていれば、おひとり様、高齢おふたり様の檀家さんを最期まで守り切ることができるでしょう。
但し、人生100年時代、認知症になるリスクもありますし、臨終期は約7割の人が意思表示が困難になるというデータもあります。
成年後見など医療福祉分野にも精通した行政書士の存在は非常に貴重価値なのです。
5. 行政書士と連携するメリット
- 遺言の適法性確保:寄付を実現できるよう、法定遺言事項に即した遺言を作成。
- 遺留分への配慮:相続人の権利を踏まえ、争いのない遺贈計画を提案。
- 死後事務委任契約の整備:葬儀・納骨・永代供養を確実に住職に任せられる契約をサポート。
- 寺院の信頼向上:「法務の専門家と連携しています」と伝えれば、檀家からの安心感が高まる。
まとめ
遺言と死後事務委任契約は、それぞれ役割が異なります。
財産(寄付・遺贈)は遺言で、葬儀や供養などの事務は死後事務委任契約でという棲み分けを理解することが大切です。
「死んだらお寺に寄付したい」「住職に葬儀を頼みたい」という檀家の思いを実現するには、住職がこれらを理解し、行政書士等と連携することが不可欠です。
(財産額が大きく相続税計算等が必要になる場合は税理士とも協業します。)
また、宗教法人として遺贈を受け入れる準備もございますので一度ご相談いただければと思います。
(プラスの財産だけを遺贈してもらうのか、マイナスも含めて包括遺贈まで引き受けるのかなど細かな条件調整は各お寺、ご住職のお考えも反映する必要があります)
【対応エリア】
富山市・高岡市・射水市・魚津市・黒部市・滑川市・砺波市・南砺市・氷見市・小矢部市・ 上市町・立山町・入善町・朝日町 など、富山県全域に対応しております。
今日もご縁に感謝!