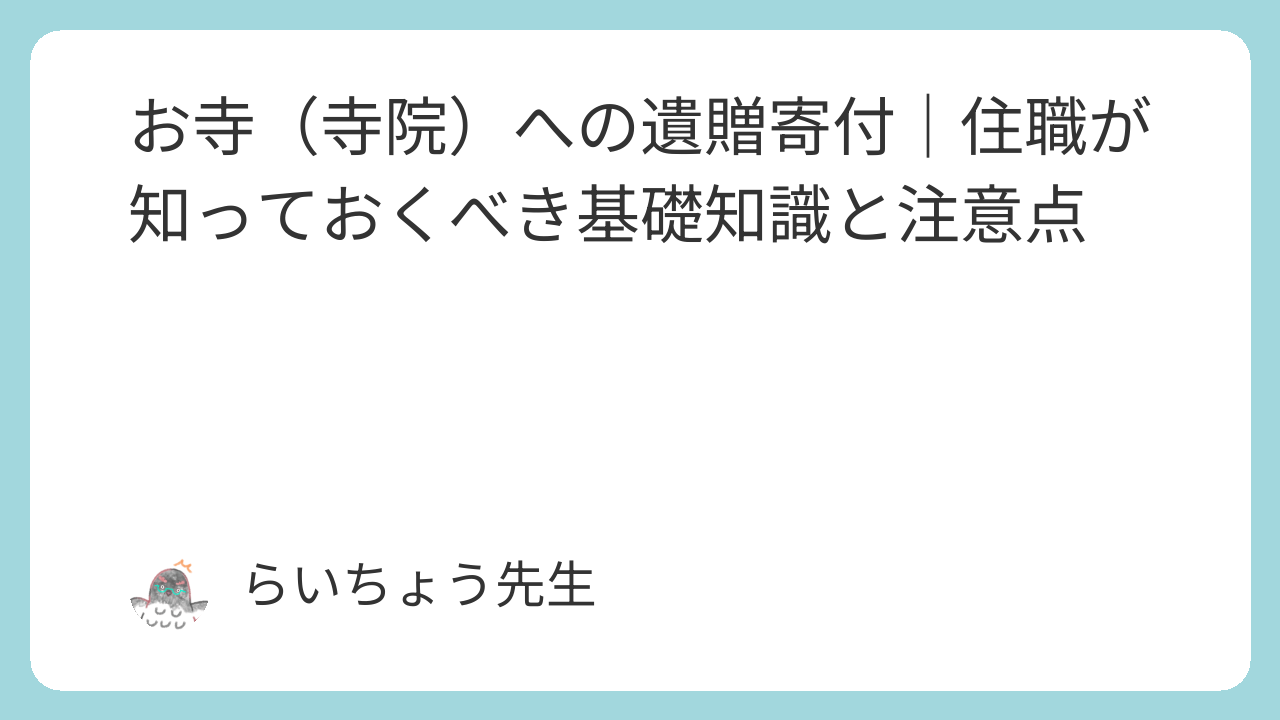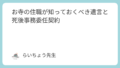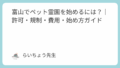「死んだらお寺に寄付したい」と檀家さんから相談を受けることは珍しくありません。
「お気持ちだけ頂きますよ」と返答していませんか?
時代は少子高齢化、無縁の時代を迎え、行く手なき財産が生まれる現実もあります。
もし、長年付き合ってきた檀家さん本当にお寺に財産を渡したいと思っていたら?
遺言書による遺贈が必要です。本記事では、寺院法務の観点から遺贈寄付の仕組みと注意点を整理します。
1. 遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、遺言によって財産の一部を特定の団体や個人に贈与することを指します。
お寺に対して檀家が「死後に寄付したい」と希望する場合、その意思を法的に有効にするには遺言書に「○○寺に遺贈する」と明記する必要があります。
口約束や手紙では効力はなく、遺言がなければ相続財産は自動的に相続人へ承継されます。
相続人が不存在の場合は国庫へ帰属して行きます。
2. なぜ遺贈寄付を学ぶべきか(寺院側の意義)
- 檀家の希望を実現:「死後に寄付したい」という声に正しく対応できる。
- 寺院経営の安定:永代供養や施設維持に充てられる財源を確保できる。
- 信頼関係の強化:住職が遺言や遺贈の知識を持つことで、檀家から「頼れる存在」として信頼を得られる。
3. 遺言でできること・できないこと
遺言は民法で「法定遺言事項」が定められており、それ以外のことは効力を持ちません。
- 財産の承継(相続分の指定、遺贈)
- 遺言執行者の指定
- 相続人の廃除・その取消し
- 祭祀承継者の指定(仏壇や墓の承継)
これ以外のこと、例えば「葬儀を○○寺で行ってほしい」といった希望は遺言では効力を持ちません。
その場合は死後事務委任契約で別途定める必要があります。
また、公序良俗や社会通念に反する内容は好ましくありません。
4. 遺贈寄付の注意点
- 遺贈として明記が必要:「遺贈する」と明記することが大切です。
- 遺留分への配慮:相続人には法律で守られた取り分(遺留分)があり、それを侵害すると争いの原因になります。作成時に相続人調査を行い円満な内容で遺贈ができるような内容にしておく必要があります。また、相続人がいる場合、相続人の気持ちにも配慮し寺院側から財産の大半を遺贈するよう求めることはあってはならないことです。
- 遺言執行者を指定:実際に手続きを進める遺言執行者を指定しておくと確実です。
人生100年時代、途中で認知症になることも考えられます。成年後見人制度をよく理解し自らが専門職後見人として責務を果たせる専門職を選ぶと良いでしょう。
遺言作成はどの行政書士もできますが、高齢の行政書士の場合体調などの理由から依頼者の死亡より先に廃業するリスクもありますので年齢は考慮した方が良いです。 - 遺贈を受け入れる準備がある:遺贈にも種類がありマイナス財産まで受け入れするのか、不動産などの現物も引き受けるのかなどの細かい点の調整作業が必要です。
5. 税務のポイント
遺贈寄付は税務上の扱いにも注意が必要です。
- 相続税の非課税:宗教法人などに対する遺贈は相続税がかからないケースがほとんどです。
- 税理士との連携:大口の遺贈寄付を受ける場合は、必ず税理士に確認し、適正に処理することが大切です。不動産なども受け入れる場合は申告が必要になります。
行政書士らいちょう事務所では、遺贈をする檀家さんの意思と、寺院様のメリットを優先し相続税発生が予見されるケースは提携している税理士との協業で行います。
6. 行政書士と連携するメリット
- 遺言作成のサポート:法定遺言事項に沿った遺言を作成し、寺院への寄付遺贈を確実にする。
- 遺留分トラブルを防止:相続人の権利を侵害しない遺贈計画を立てられる。
- 死後事務委任契約の整備:葬儀・永代供養を寺院に任せられる契約を支援。
- 税理士との連携:遺贈寄付に関する相続税等の税務リスクを最小化。
まとめ
お寺にとって遺贈寄付は、檀家の信頼に応え、寺院経営を支える重要な仕組みです。
ただし、寄付は遺言で遺贈として書いてもらうことが必須であり、遺留分や税務への配慮も欠かせません。
「死んだらお寺に寄付したい」という檀家の希望を法的に実現するために、住職は遺言と死後事務委任契約を学び、行政書士や税理士と連携することが不可欠です。
勿論、人生100年時代を支える医療福祉の知見と併せて提供いたします。
【対応エリア】
富山市・高岡市・射水市・魚津市・黒部市・滑川市・砺波市・南砺市・氷見市・小矢部市・ 上市町・立山町・入善町・朝日町 など、富山県全域に対応しております。
今日もご縁に感謝!