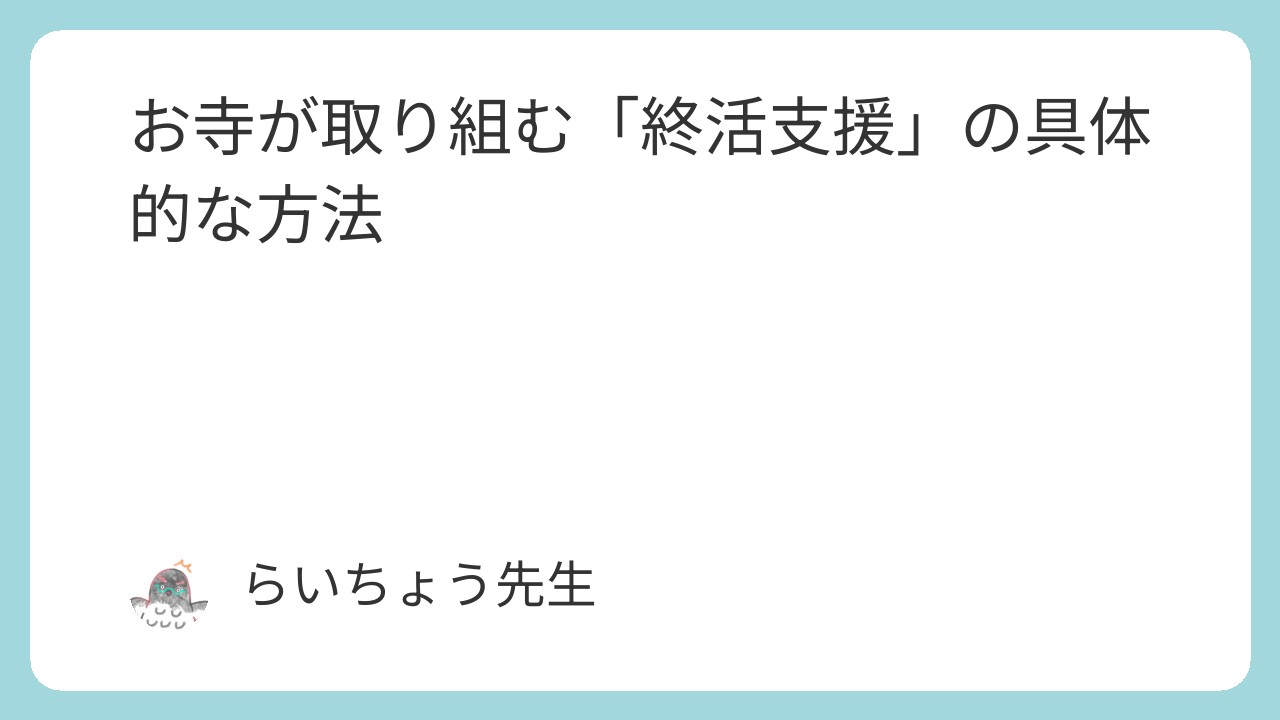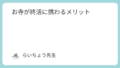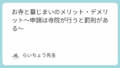檀家や地域の方に向けて、お寺が今すぐ始められる終活支援の方法を整理しました。難しい準備は不要で、信頼関係を深めるきっかけになります。
うちの檀家さんは興味が無いからと思っているともったいない!
実際に小規模納骨堂を運営して経営拡大している寺院さんや、若手跡継ぎさんが見つかったという事例もあります。
1. 終活セミナー(法話+行政書士等の専門家)
ご住職の法話に加えて、行政書士や税理士などの専門家を招き、
「遺言の基本」「相続の準備」「墓じまいの流れ」など具体的なテーマで話す形式です。
檀家さんは「心」と「手続き」の両面で学べるので満足度が高くなります。
ここで重要なのは、お相手が高齢という部分。法律だけに詳しい専門家を招いてしまうと「難しくってよく分からない会」になってしまうおそれも。
私が実際に検討している例ですが、老人クラブと連携して「相続落語」など娯楽要素を入れたりしています。
私自身も看護師でしたので、介護予防体操から法務知識まで幅広くカバーします。
2. 墓じまい相談会
行政書士や石材店と連携して「墓じまい相談会」を開催する方法です。
墓じまい後の「永代供養」「納骨堂」「散骨」などの選択肢も合わせて紹介できます。
お寺にとっては檀家様が減るとお考えかもしれませんが、「形を変える」提案で良いつながりが維持できているケースもあります。
特に足腰が弱くなってきた高齢者や遠距離に次の世代がいる場合、参りたいけど参れない。言い出しにくいという気持ちは必ずあります。
寺院側からの提案はぐっと刺さりますし、荒廃した墓を生じさせない予防策にもなります。
3. 納骨堂・永代供養見学会
実際の納骨堂や永代供養墓を見学していただくことで、
将来の安心感を持ってもらう取り組みです。
見学会はお寺に足を運んでもらうきっかけとして効果的です。
納骨堂や樹木葬のニーズは増加しています。
一方で菩提寺を変えたくないというお気持ちの高齢者もいますが、施設がなければ対応出来ません。
宗派を問わず受け入れをしたり、バリアフリーで参拝ができる納骨堂は大人気です。
4. エンディングノート配布
エンディングノートをお寺から配布するだけでも、檀家さんの意識は大きく変わります。
配布後に「書き方ミニ講座」を開催すれば、自然に終活の話題を広げられます。
お寺オリジナルのエンディングノート作成のご相談にも応じています。
書籍を作るなんて、と身構えなくても大丈夫です。
ネット上で作って必要な時に冊子化して届けてもらうサービスもあり、1冊1000円以下でできますよ。
法話や何かあったときのお手続きなどお寺との連絡ノートのような使い方も面白いですね。
5. セミナーの開き方 例
- テーマを絞る:「遺言の基礎」「墓じまいの流れ」など具体的な一つに絞るとよいのでテーマを相談しましょう。
- 法話+専門家講話の組み合わせ:ご住職が「生き方・死生観」を話し、私が体操や法務知識を話します。時間配分はご住職の指示通りに作成します。
- 開催時期:報恩講など檀家が集まりやすい行事に合わせると自然に参加してもらえます。
- 告知方法:お寺の掲示板、会報、ホームページでの告知が良いです。
事前に寄稿をさせていただけるとスムーズです。
先進的な寺院ではメルマガ方式を検討しているところもありますよ。 - アフターフォロー:終了後に「個別相談コーナー」を設けます。
継続的に行う事がキーなので反応がいまいちでも数回続けてみると、ぐっと手応えが出てくる時期があります。費用がほとんどかからないのでデメリットはあまりありません。
まとめ
お寺が終活に関わる方法は、特別な準備をしなくても始められるものが多くあります。
セミナー・相談会・見学会・資料配布などを通じて、檀家や地域に「安心」を届けられます。
そして、法務面のサポートが必要なときには行政書士が対応します。
「うちのお寺でも終活支援を始めたい」と思われた方は、ぜひお声がけください。
行政書士らいちょう事務所は富山、北陸でもほとんどいない看護師・社会福祉士他を所持する高齢者対応のエキスパートです。
【対応エリア】
富山県全域(富山市・高岡市・射水市・魚津市・黒部市・滑川市・砺波市・南砺市・氷見市・小矢部市・ 上市町・立山町・入善町・朝日町)に対応しております。
上記以外の地域の方も、まずはお気軽にご相談ください。
日々、ご縁に感謝!