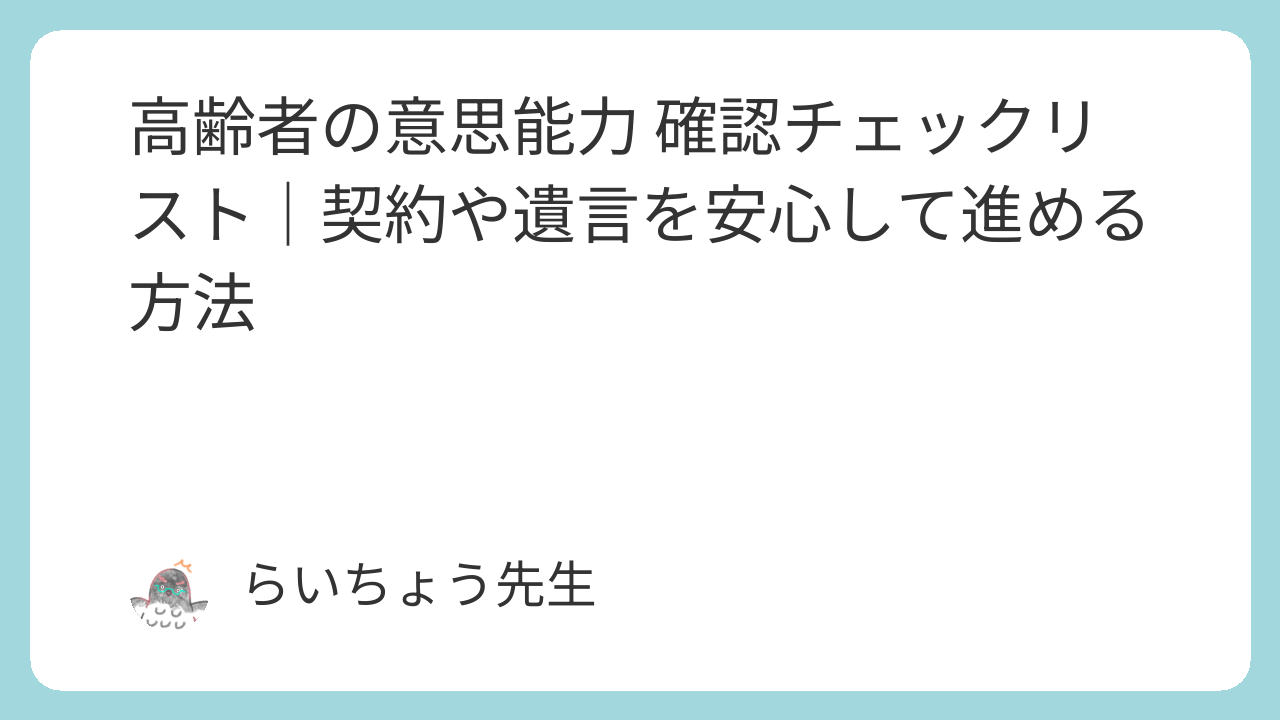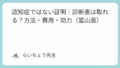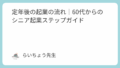高齢化が進む中、契約や遺言をめぐるトラブルは年々増えています。
「本人はきちんと理解していたのか?」「契約は有効なのか?」——こうした疑問の多くは、高齢者の意思能力の確認不足から生じます。
この記事では、民法の考え方や認知症と物忘れの違いを踏まえながら、契約や遺言の場面で役立つ意思能力の確認チェックリストを紹介します。
認知症と物忘れの違い
- 加齢による物忘れ
・体験の一部を忘れる
・日常生活には大きな支障がない
・「あ、そうだった」と思い出せることも多い - 認知症による記憶障害
・体験全体を忘れる
・記憶障害に加え、判断力や理解力の低下が見られる
・日常生活に支障が出る
・医学的な所見を伴う(脳萎縮や脳出血痕跡など)
👉 「物忘れ=契約できない」ではなく、軽度の認知症であっても契約や遺言を有効に行えるケースはある認識は重要です。
民法と意思能力の関係
民法3条の2では、
「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかった時はその法律行為は無効とする」
と定められています。
つまり、本人に契約内容を理解し判断できる力がなければ、その契約や遺言は最初から無効です。
ただし「意思能力があるかどうか」を一律で決める基準はなく、個別のケースごとに判断されるのが実情です。
契約の不成立や契約無効が生じる可能性があることは、高齢者との契約においては頭に入れておくべきでしょう。
高齢者の意思能力 確認チェックリスト
実際の契約や遺言の立会いで使えるチェック項目例です。
会話や観察を通して、以下を確認していきます。
| チェック項目 | 確認の視点 | □ |
|---|---|---|
| 自分で電話をして来訪予約をしたか | 自立した意思表示ができているか | □ |
| 契約場所まで自分で交通手段を手配したか | 行動能力・判断力の一端 | □ |
| 本人に直接聞き取りを行ったか | 代理人ではなく本人の意思確認が原則 | □ |
| 年齢・生活状況(独居か家族同居か) | 支援体制の有無を把握 | □ |
| 家族は今回の契約を知っているか | 家族間のトラブル防止 | □ |
| 契約動機に不合理さはないか | 家族トラブルの発見 | □ |
| 対話で意思疎通がスムーズか | 言葉や表情で理解度を推測 | □ |
| 身なりに不自然さはないか | 着こなしの乱れ・裏表など | □ |
| 金銭管理を自力でしているか | 日常生活力の判断材料 | □ |
| 介護認定の有無 | 要介護度から判断力を推測 | □ |
| 健康状態・既往歴 | 認知症を疑う疾患歴の有無 | □ |
| 同席者の有無と関与度 | 本人の意思が尊重されているか | □ |
| 取引代理人がいる場合、権限を確認 | 代理権限の有効性 | □ |
| 成年後見制度を利用していないか | 利用中なら契約は後見人の権限範囲内 | □ |
👉 医学的な検査(HDS-R、MMSE)は医療の専門領域なので通常は不要と考えております。実施者の能力や場所などにも結果が左右されるため、負担をかける割りには正確さに欠ける結果が多く見られます。
確認チェックは自然な会話や行動の中から観察しますが、必ず実施観察記録を残しておかないとチェックしなかったに等しいということも覚えておいてください。
なお、契約の金額や期間など重要と思われる内容については本人の言葉通りにセリフで記載する方が良いでしょう。
納得していた様子あり。と記録するよりも、「金額も80万円で、永代供養なら納骨堂にした方がいいかなと思うんです」など納得している様子が分かる記録ということですね。
また、高額の契約など本人にとって多大な影響が予想される場合は、何度か場面を変えてチェックすることも検討した方がいいでしょう。
チェック内容と、頻度で意思確認の結果をより、信頼度の高いものにする工夫です。
家族構成は把握した方が良いです。意思能力と関係ないよね?と思うかもしれませんが、意思能力が争われる場合、家族・親族・相続人の争いが根底にある場合が多いです。
高齢者本人の希望するように契約がすすむようサポートしますが、残念ながら認知症がすすんでいて単独での契約断念の判断に至る場合もあります。
医師の診断書は必要?限界は?
- 診断書が役立つ場面
・相続人や家族のトラブルが予見される場合
・不動産取引や大口の金融契約で求められるとき
- 診断書の限界
医師が書けるのは「当日の医学的所見」だけで、法律上の意思能力を断定する立場にはありません。
裁判になると、カルテ・介護保険意見書・審査資料など、複数の証拠が総合的に評価されます。
契約の段階では見れなかった資料も全て裁判資料になります。
要介護2~3程度であり、すでに何らかの介護サービスを受けている場合は、申請理由にも注意が必要です。身体的な理由かそれとも認知力にも低下を示す所見があったのか。
診断書はその検査や診断を受けた一瞬を切り取って評価するものですが、介護サービスの記録などは継続的に状態を評価するものとして扱われているようです。
まとめ
- 「物忘れ」と「認知症」は別物。認知症だからといって即「意思能力なし」ではない。
- 民法3条の2では意思能力がなければ契約や遺言は無効としているが基準が明確ではない。
- 意思能力の有無は、複合的に観察して判断していく。
- 医師の診断書は補強資料として有効だが、それだけで絶対に証明できるわけではない。
富山でのご相談は「行政書士らいちょう事務所」へ
看護師・社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネジャー、行政書士資格者。20年ほど医療福祉現場に勤務。高齢者の終活サポートを行っています。
【対応エリア】
富山市・高岡市・射水市・魚津市・黒部市・滑川市・砺波市・南砺市・氷見市・小矢部市・ 上市町・立山町・入善町・朝日町 など、富山県全域に対応しております。